解題としての小峰さちこ
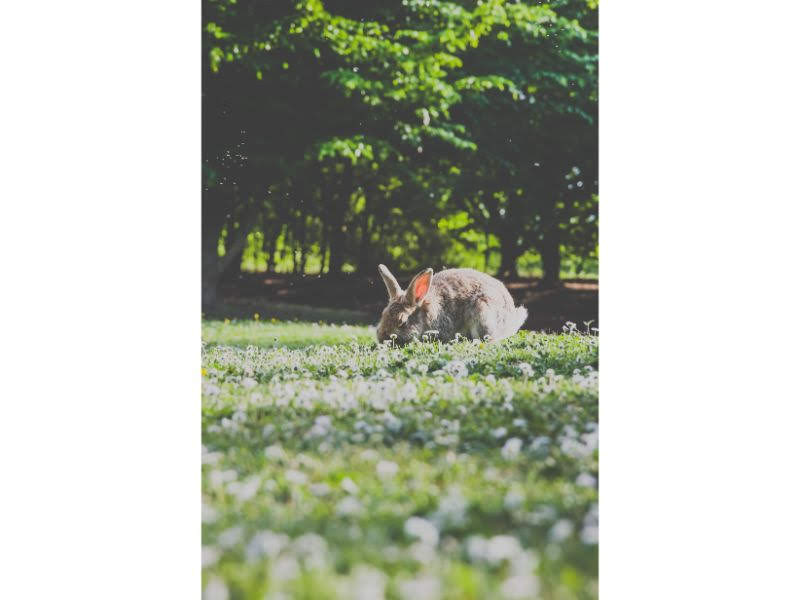
この記事は@shinabitanoriが自作の自家解説をするものです。そういうのが苦手な方は読まないでください。
さちこの話
私はここで私自身の話をしようと思う。自家解説というやつだ。理由は、なんか書けそうだしなんとなく書こうと思ったからというのが一番大きいのだけど、まず、最近、以前ほどたくさんは短歌をつくらなくなったなかで、自分の作品を読み返していて、こういうのがしたかったんだなというのが少し客観的に見えてきたような気がしたので。あとは、最近そんなに新しい作品を流さなくなったし、読まれるのを待っていても誰も読みにこないだろうというのもある。なら、自分で読み直そうみたいな。そんな感じだ。
「小峰さちこ」としての作品は星空文庫などにまとまってあげられているので、そちらで読むことができる(本当は「小峰さちこ」という筆名を使ったことはなくて、いつも「さちこ」とだけ名乗っているのだけれど)。これまでそれなりの数の作品をあげてきたけれど、彼というか、彼女というか、まあどちらにせよ私だが、ともかく、この人の作品らしいなと私自身が思った一群の作品は、たとえば以下のリンクから読むことができる。
自選50首
町はもう魔法少女の夢のなか大人のいない戦争がある
この「自選50首」は以前、ひざみろさんが五十首評の企画をやったときに見せたもので、以下の記事で評をしてもらった。
自選五十首評① さちこさん|御殿山みなみ|note
今年に入ってから、一首評をしっかりやっていこうという気持ちになりつつ、歌人評なるものにもチャレンジしていきたいなあ、でも中々ハードルが高いなあと感じていた時に、我ながらナイスなアイデアを思い付いた。 それは、送られてきた自選五十首からその人を評するというもの。五十なる数は結構なものだから、歌人評を十分できる分量だ。しかも、読むのもたった五十首でいいときた。これはかなりお得なシステムだ。 ...
この記事のなかでひざみろさんにはいくつかの観点を挙げてもらいながら、興味深い読みをしてもらった。とりわけ「肯定的なときの虚構感」というのはなるほどなという感じだった。というか、後出しで申し訳ないのだけれど、現実にないものを描くというのがさちことしての作品のひとつの軸であることは以前にもべつの場所で何度か明かしている。たとえば、この記事にまとめたツイートなどの言い方だと、どうやら次のように言っていた。
一般論はそろそろ語りたいことがないので、私の場合の話をします。私の場合、文学というのはフィクションとノンフィクションを架橋するためにあるものだと考えていて、そういう機能を果たしうる作品づくりをめざしています
そのための手法じゃないですけど、リアルな私の語りを媒介項としつつアーバンファンタジー的な荒唐無稽な描写を混ぜるというのはよくやります
ひざみろさんはこういうレトリックについて本心をフィルタリングする照れ隠しなんじゃないかと言っていたわけだけれど、こういったいわばないものをあるものとして描くのは、さちこという詠み手の手癖みたいなものだと思う。さちこ自身は「フィクションとノンフィクションを架橋する」という言い方をしたのだが、大げさにいうと、そういうふうに存在と非存在が交差する地点にこそ、彼(彼女)という作中主体は佇んでいる。
ないとあるとのあわい
ないものをあるものとして描くというのは、たとえばこういうフィクションの作品だ。
窓口でおとな一人と告げて買う おとな一人で浸かるひだまり
「おとな一人で浸かるひだまり」なんて、実際にはどこにも売っていない。だからこれはフィクションなのだといえばそうなのだろう。あるいは次も、そういうフィクションの短歌だ。
こっそりと心に虹を飼っている 餌はヨーグルトをよく食べる
ここで「心に飼っている」という「虹」は、少なくとも実体としては存在しない。だから、ここでいう「虹」とは非存在なのだが、それについて「餌はヨーグルトをよく食べる」という具体的な描写を重ねることで、「虹」があたかも存在するかのように描いている。
おおぞらに硝子のさかな泳ぎいて記憶は太古へと遡行する
これもそうだ。実際には、空に硝子の魚など、いない。けれど、それが実際にいるものとして扱われることで「記憶は太古へと遡行する」。次も、同じ構造をしている。
ベランダに大っきなイリエワニがいていますぐきみに会えなきゃ困る
ベランダにイリエワニなどなかなかいない。そりゃそうだ。それでも、そのことがもととなる論理は依然としてきちんとはたらいていて、だから「いますぐきみに会えなきゃ困る」のだという。
このように、ないものをあたかもあるものとして描くというのは、しかし、そもそも特別なレトリックではない。多くの歌人はそういう作品をむしろしばしば量産している。それでもそれが何かさちことしての作品に特徴的なものとしてあらわれているように感じられるのは、彼(彼女)自身が「アーバンファンタジー的」だという言い方をした、フィクションとノンフィクションが陸続しているような独特の雰囲気に原因がある。
そこでは、ときにあるべきはずのものがないものとして描かれる。
ぶらんこに立って乗ること愛なんかなくてもやっていけていること
この作品は「愛」というあるべき(とされる)ものの不在をそのまま取り上げている。あるいは次では、実際にあるものの内部に、ないものがある。
鏡月のボトルの中に海があり僕らのifを見せつけてくる
比喩といえばそれまでだが、ふつう鏡月のボトルの中に海はない。「僕らのif」にいたってはまさに反実仮想であり、実際存在しないものだ。次は、ないもののなかに、あるものがある。
でもたぶんのんのんびよりりぴーとの世界にだって貧困はあるよ
「のんのんびよりりぴーと」というのは、女の子たちが田舎で過ごす日常を描いたTVアニメ作品のことだ。その世界は、現実にはない。一方で、貧困は、具体物として目に見えないかもしれないが、確かにこの世界のなかに実在している。
非存在に向ける声
町はもう魔法少女の夢のなか大人のいない戦争がある
これも先ほどと同じ構造の作品だろう。魔法少女はいない。したがって、魔法少女の夢とはフィクションなのだが、一方で「大人のいない戦争」は少なくともその世界の内部にはあるものとして描かれる。そして、それは、おそらく、ときにこの世界にもノンフィクションとして実在している。
このように存在(あるとされるもの)と非存在(ないとされるもの)とのあわいを意図的にずらしながら作品を鑑賞していくとき、さちこの作品は独特な地平のなかに開けてくる。そこでは、一見するとあるかのように描かれているものも実はないのかもしれないし、同様に、ないものとして描かれる非存在も実体として立ち現れるときを予期しているのかもしれない。
そのような地点にあって、ことさら意味を帯びて響くもののひとつが、ひざみろさんもさちこの特徴のひとつとして指摘した〈呼びかけ〉である。
けどやっぱおれら大人になっちゃってよかったんだよ。梅酒うまいし。
サバンナの象のうんこの心境で傍にいるから何でも言えよ
だいじょうぶお前は雨じゃないんだよだから安心して落ちてこい
これらの呼びかけはその対象として、なんというか、誰でもないような他者を予感させる。彼らには具体的な顔がないような感じがする。ひざみろさんはそのことを「属性に向かって呼びかけている」という言い方をしたが、そんな感じだ。実際、たぶんだが、意識の問題として、これらの呼びかけの主体には呼びかけるべき対象の姿が実体的なイメージとして見えているのではない。そこでは順序が逆転している。むしろそうして呼びかけるという行為そのことが、呼びかけられる対象の姿をはじめて浮き彫りにして、立ち上がらせるのである。
パインアメ越しでいいから5秒間瞳をとじてキスしてくれよ
だから、さちこの呼びかけにはこういう意味のわからない譲歩が添えられたりする。それらは確かに論理形式ではあるが、論理としては明らかに破綻している。考えてみれば、梅酒が美味しいことと大人になってよかったことだって理由としては必ずしも直結しないものだったし、サバンナの象のうんこの心境で傍にいられても弱音を吐き出すための助けにはならないはずだ。つまり、ここで呼びかけられるべき対象とは、いわば、呼びかけられるべき理由を正しい形式では持ちえなかった一群の人たちなのだが、これらの呼びかけは彼らに論理形式を無理やりあてがうことによって、彼らに本来かけられるべきだった声を届けることを可能にしているのである。
彼(彼女)自身の弱さ
このような存在以前の非存在に向けた呼びかけが成立するためには、呼びかける主体自身が呼びかけられる対象の一員であるような〈当事者性〉とでもいうべき、ある種の気づきが必要になる。さちこの作品の主体は、どちらかというとそうやって他者に声をかけてもらうべき側の人間であり、いわゆる〈強い〉人間ではない。一連の作品を注意深く読み進めていくと、主体自身が主題である短歌は多くなく、あるにしても総じて反実仮想的なものが目立つ。
向日葵になって貴女の唯一の寄る辺のように抱かれていたい
うれぴよと君が云うたび生まれ来るひよこのような者でありたい
この主体は他ならない自分の弱さを傷として抱えていて、そのことをコンプレックスに感じている。
ストロングゼロでひとりで酔っているわたしわたしがいちばんきらい
「ひとりで酔っているわたし」が「いちばんきらい」だという彼(彼女)は、そうして彼(彼女)自身を含めた姿なき他者の声に応じ、対話を繰り返す。その背景に通底しているのは、自らの弱さへの自認であり、そのような弱さを抱えざるをえない他者(あるいは自分自身)への共感だろう。
ほんとうは私もいつかペンギンになるのが夢で上京したの
さちこの短歌は、いわゆる生活詠と呼ばれるような地に足のついた感じのするものではない。それらはしばしば虚構的で、おどけたような、ありえない景を提示してくるものだ。それが照れ隠しからはじまったものだったのかは私自身よくわからないのだが、さちことしての作歌は、正しい形式では要領を得ないながらも弱い立場にある〈私〉たち自身に共感しながら、そうすることによって彼らを確かな姿をもつ存在に引き上げようとするようなおこないだったのではなかったか。
ここで述べたことはもちろん、作者としてつねにこういうことを意識して作歌していたというものではないし、だからこれが読み筋として唯一の正解だというようなものではない。ただ、こういうふうな読みのもとに自分の作品を捉え直すとき、私も案外がんばって短歌をやっていたんじゃないかと自分をひとつ肯定できるような気がして、嬉しく感じるものもあった。
